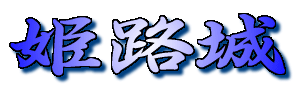
世界文化遺産「姫路城」
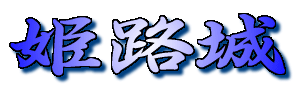

国宝姫路城は天下の名城である。つい先頃、世界文化遺産に指定されたばかりである。別名白鷺城とも言われ、
その白く優美な姿は例えようのない美しさである。
私達家族は3月8日淡路島からの帰りに立ち寄った。山陽自動車道を途中から降り姫路市内に向かった。行きも
帰りも状況は同じだったが、どうしてこうアクセスに不便な町なのだろうと言うのが率直な感想であった。そして、
この日はあいにくの曇り空であった。どんよりとした低い雲は、今にも降ってきそうな感じであった。悪い予感は
的中し、お城についた頃には、ぽつぽつと冬の終わりの冷たい雨が降り始めた。ここまで来て引き返すわけには
行かないので、城下の市の地下駐車場に車を停めてお城に向かった。
日本国中、多くの城が堀を埋めたてられている中で、姫路城の大きな内堀は満々と水を湛えていた。今でも
城としての機能は十分備えているのである。この堀に架かった橋を渡り、城門をくぐり、城中にはいると西の丸
という広い広場がある。広場は草地になっており、花見時には格好の見物席になるようだ。この場所から天守閣
を含む城の中心部が一望できる。しかし、あまりにも遠く離れすぎていて城の迫力は伝わってこない。

大きな内堀には満々と水を湛えていた。姫路城全景を眺める。 この広場を横切り、あるいは迂回して管理事務所まで歩いて行く。こんなお天気にも関わらず大勢の人で
賑わっていた。管理事務所受付で入場券を買い、パンフレットを貰い中に入る。ここには菱の門と呼ばれている
大きな門がある。
このまま、まっすぐに、いの門、ろの門、はの門とくぐって行っても良いのだが、私達は長い渡り廊下のようになった
渡櫓を歩いてみた。薄暗い廊下が延々と続き、廊下の脇にはいくつもの部屋がある。薄暗い部屋からは明るい
外の景色を眺めることが出来る。窓からは日本庭園が見えている。今はまだ蕾の固い桜の木があり、花の頃は
さぞかし美しい事だろうと想像された。化粧櫓は千姫のために建てられた建物だけあって、他の建物のような
無骨さはなく優美な造りである。大きな畳敷きの部屋には千姫を模したと言われている人形が貝合わせに興じて
いる姿が再現されていた。

長い長い渡櫓の外側、化粧櫓での千姫を模したと言われている展示 化粧櫓を後に一旦外に出る。そして、はの門をくぐって、いよいよ本丸の中に入る。建物の東西には大きな柱が
立っている。これが本丸を支えている心柱だ。資料によると根本の直径が95センチとの事である。この心柱から
東西南北に幾本もの梁が出ており、この梁が各層の床や大きく張り出した屋根を支えている。曲がった木をうまく
組み合わせた実に巧みな構造になっている。姫路城は先の阪神大震災の時、壁は落ちたもののこの木組みは
びくともしなかった。やはり、この複雑な木組み構造が揺れを吸収したのであろうか。

色んな角度から天守閣を眺めてみた 
見る角度によって様々な姿を見せる 
近くから見ると多層に重なった屋根と白壁のコントラストがとても美しい 城の中も先ほど歩いてきた渡櫓と同じように暗かった。そして急な階段をいくつも上らなければならない。昔の
事だから当たり前と言ってしまえばそれまでだが、当時の人々の不自由さが偲ばれる。各層にはところどころに
説明書きがあり、展示物も置かれていた。鎧や刀、鉄砲もあれば槍もあった。

城内の展示物の一部、左は天守閣の木組み構造を模したもの いくつもの急な階段を上りきると、やがて最上階に着く。ここには神棚が祀られている。祀られているのは
この天守の丘にあった地主神をお祀りした長壁神社である。ここは、この城の中心となるところである。四方には
窓があり姫路市内を一望できる。こうして眺めてみると、如何にこの城の規模が大きいかよく分かる。敷地面積は
二万五千坪との事で、徳川幕府の重鎮であった池田や本多と言った人達の居城であった事も頷けるのである。

天守閣最上階の窓から姫路市内を一望する 
左の写真は姫路城の敷地の一角、その広さが分かる。 城をバックにした私の近影 私達は世界文化遺産である姫路城の外も中も十分見学し、再びお城の外に出た。そして、お菊井戸や腹切丸など
といったところを見て管理事務所近くへ戻ってきた。この間も雨は降り続いていた。駐車場に戻った頃には本格的な
降りになった。夕方のラッシュと重なって混雑する市内を抜け、やっとの思いで再び山陽自動車道に出た。ますます
雨はひどくなってきたようだった。
残念だったのは季節が冬であったこと、そしてお天気が悪かった事である。これで新緑の頃、晴れ上がった青空の
下で眺めたら、姫路城の美しさがいっそう際だっていたことであろうと残念でならない。
2003年4月9日掲載
|
|
|
|