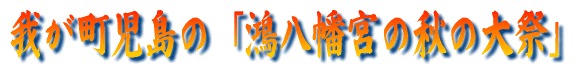
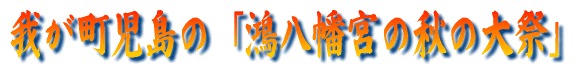


鴻八幡宮は私達の氏神様である。信仰が薄くなった今日とは言え、夏祭り、秋祭り、お正月、厄払い、
七五三と折に触れてお宮との縁は切れない。
鴻八幡宮は児島の下の町にある。小高い山の中腹にある。境内からは児島湾が一望できる。
大抵のお宮は正面が石段になっているものだが、鴻八幡宮は土だけの坂道となっている。
これは恒例の秋祭りの行事と密接な関係がありそうだ。鴻八幡宮は周辺地域では有名な
段じりの出るお祭りである。段じりは周辺の部落毎に一基ずつ持っており、祭り当日には
午前の部、午後の部と分かれて神社の境内に登ってくる。従って、車輪の着いた段じりだからこそ
石段ではなく、土の坂道となっているようだ。段じりは坂道を登るときにも、降りて行くときにも
にぎやかに笛や太鼓、鐘や鼓を打ち鳴らしながら、段じりを上げたり下げたりと練り上げる。
観衆は両サイドやお宮の門のところに陣取って、この様子を眺めるのだ。
段じりがお払いを受けるために境内にいるとき、坂の上り下りの時、町内を練り歩くときと、
それぞれの場面において、お囃子が異なる。都合、七曲のお囃子を使い分けている。
実に優雅なものである。お囃子の種類は下記の通りである。2000年の秋祭りには
倉敷ケーブルテレビが取材に来ており、中継録画を行っていた。女性アナウンサーが
段じりの中でも一等由緒深いとされている傘鉾の上に載せて貰って、おっかなびっくりの
様子であった。(下記の写真)

これは傘鉾の写真である。傘鉾が一番に登り、一番に降りる では、ここでお囃子の種類を紹介しておこう。
(1)だんぎれ囃子(いざ出発とか、これから始まりますよという合図)
(2)おやじ(上がりはとも言う)鳥居をくぐり神社の境内までの坂道を登るとき
(3)祇園囃子(境内にてお払いを受け、段じりを休ませているとき)
(4)神楽囃子(社前にて神様に奉納する囃子)
(5)下がりは囃子(文字通り境内から段じりを下ろし、坂道を下るとき)
(6)おひゃりこ囃子(だんじりが停止、または休憩中に演奏される)
(7)信楽囃子(兵庫囃子)地元に帰って行くとき、ほっとしたひとときであろうか
信楽囃子が一番なじみの深いお囃子(チョイヤレとかラットラットと言った合いの手が入る)
これら全ては伝統行事として岡山県重要無形文化財に指定されている。
2001年の秋祭りは10月13(土),14(日)となっている。
しゃぎりリンク
沖熊保存会で作っているサイト 「鴻八幡祭りばやし」
|
|
|
|