
虎さんの旅した町「高梁」

備中高梁市は臥牛山の麓に広がる歴史と文化の街である。かつて「フーテンの寅さん」が大ヒット作で
あった頃、この地を舞台に撮影が行われた事がある。寅さんの愛すべき妹「さくら」の旦那さんの「博」
の出身地がここ高梁市という設定であった。私もこの映画を見たが、地方の町らしい静かで落ち着いた
雰囲気が出ていて良かったように記憶している。


撮影現場としては、豊かな自然に囲まれたこの地が寅さんシリーズに出てくる町の雰囲気として
適していたのであろう。細い路地、築地塀、お寺に続く坂道等、いずれもが人情味あふれる映画の
小道具となっている。今も町並みは撮影当時と変わらない。


この町の象徴とも言うべき山は臥牛山である。遠くから眺めると、牛が伏せているように見えることから
この名前が付けられたと聞いている。現存する城の中で日本で一番高い山城と言われる備中松山城は
臥牛山の一つ標高430メートルの小松山の山頂に築かれている。重要文化財の天守閣は今も昔の
ままの姿で残っており、関連の建物は復元整備が行われている。


城主は様々に変わったが、最後の城主となったのは幕末の老中、板倉であった。
板倉藩には藩の逼迫した財政を立て直したという山田方谷がいた。山田方谷は幕末の英雄とも
言われている長岡藩の河合継之助も教えを請いに来たほどに、天下に名の知れた人物であった。
その他、この城にゆかりのある人物としては、かの有名な大石蔵之助がいる。当時城主であった
水谷家に跡継ぎがなく、城開け渡しの際、城の受け取り役として赤穂藩が選ばれた。その際、
赤穂藩から大石内蔵助が、この地を訪れている。よもやこの時、数年後に自分達もそのような
憂き目に合おうとは、大石内蔵助とて想像だにもしていなかったであろう。
この町は高梁川と間近に迫る山並みの狭い一角に開けている。その昔、高梁川には高瀬舟が行き交い、
川、道ともに交通の要衝であった。従って、鎌倉時代に城が築かれた時から、すでに戦略的にも
重要な拠点であったようだ。このように備中松山城は小さな山城ではあるが、山陰から山陽に抜ける
数少ない主要道路の重要拠点にあって、常に周辺ににらみを利かしていたのではないだろうか。
見晴らしの良い山頂に城を築いた理由も分かるような気がする。
先ほども少し触れたが、高梁の町は臥牛山と高梁川に挟まれた狭い土地に開けた細長い町である。
現在も昔の面影をとどめるものとしては、町のあちこちに残されている城下町時代の石垣と、古い寺院、
そして、わずかに保存されている当時の武家屋敷だけである。

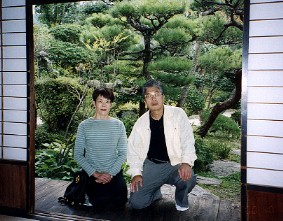
この町は第二次世界大戦においても空襲を受けなかった。従って、古いものがそのまま残った町である。
今も産業らしい産業はほとんどない。それだけに古いものが壊される事なく残されていると言うことなのだろうか。
私も家内も何度かこの町を訪れているが、十数年を経てもほとんど変化が無いというのが率直な印象である。
臥牛山へは登山道がついている。かなり急な坂道である。山はほとんど手つかずのまま保護されており、
多くの植生に恵まれ、動物達の最適なすみかとなっている。山頂へ行くには二つの方法がある。
健脚で時間のある人には山裾から一挙に山頂を目指す方法、車で来た人や足に自信のない人には
途中までシャトルバスで行く方法がある。バスの終点からは歩いて天守閣を目指す。


私が訪れた10月の上旬は秋晴れの晴天に恵まれた日であった。JRが企画したツアー客も
来ており、大変な賑わいであった。市内至るところに点在する寺の庭には、柿がたわわに実を付けており、
秋の日を受けて一幅の絵を見るような風情があった。先の地震ではさしたる被害もなかったようで
幸いな事であった。私達夫婦はお城の庭で弁当を開いた。お城の上にはぽっかりと空が開け、青空が
大きく広がっていた。上空遥かには鳥が円を描いていた。双眼鏡をのぞいていた人の話では渡り鳥の
「さしば」だと言うことだった。
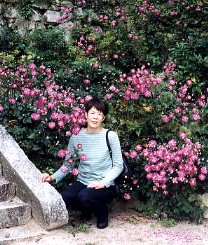
この地の名物は湯葉だそうだが、試食にとどめ、地元産の大きななし「新高」をみやげに買った。
そして、駐車場の前の酒屋さんで地酒を買ってみた。まだ、味わってはいない。
歩き疲れて、夕日が西に傾き始める頃、高梁を後にした。道縁の田圃には稲が重く穂を垂れ
収穫を待つばかりであった。秋の眩しい光りの中を寅さんをしのびつつ、高梁の町を満喫した一日であった。
高梁関連リンク
|
|
|
|