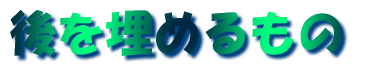
後を埋めるもの
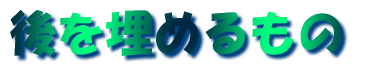
庭の草を抜くとまたそこに新しい草が生えてきます。その草は決して前の種類と同じ草ではありません。季節によっても
変わりますが、それだけではなく、それまで芽を出すことが出来なかった草が後を追うように生えてくるのです。こうして
畑と言わず、空き地と言わず、土のあるところであれば必ず草は生えてきます。
また、草の種類も大きな周期で変化しているようにも見えます。一時あれほど大騒ぎをしたセイタカアワダチソウが
最近少なくなってきました。その代わりまた他の草が生えてきました。
富士山の麓には広大な樹海が広がっています。青木ヶ原といいます。一度迷い込んだら出てこられないという深くて
広大な森です。この森の中でも同じような営みがずっと続いています。大きな木の根本には小さな木が芽を出しています。
しかし、大きな木が日光を遮って小さな木には届きません。従って、小さな木は大きな木が生きている間には、決して
大きくはなれないのです。しかし、やがて大きな木が倒れると、その後を埋めるように成長を始めます。あるものは倒れた
木の上に根を下ろし成長を続けます。このようにして森は常に生と死を繰り返しています。大木の後には必ず次の木が
控えていて空白となった空間を埋めていくのです。
同じような事は自然界だけでなく私達人間についても言えるのではないでしょうか。親子の関係もそうです。おじいさんが
亡くなったらお父さんが、お父さんが亡くなったら息子がと言うように、その後を埋めていきます。会社でも同じ事です。
上司が何かの都合でいなくなっても、心配をするほどの事はないのです。必ず代わりになる人が出てきて後を引き継いで
いきます。このように自然界では絶えることのない連鎖の帯がずっと先まで続いているのです。
歴史を振り返ってみれば良く分かります。信長の時代は信長しか統治を出来ないように考えていましたが、簡単に
秀吉が後を引き継ぎました。そして秀吉の後は家康が控えていました。このように当たり前と言えば当たり前のことが、
きちんと連鎖の帯となって絶えることなく続いているのです。
従って、私達も自分が自分がと考えずに、いつでも後に控えている人に道を譲れるように考えていたいものです。
私自身もまた後進に道を譲る日が近いことを意識しながら日々を過ごしています。
2002年10月18日掲載
|
|
|
|