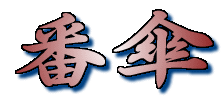
番傘
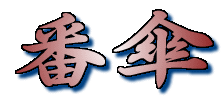
今でこそ使い捨ての代表のようになっている傘ですが、私達が子供の頃には貴重品の一つでした。置き忘れたら
必ず取りに返っていました。その頃、傘の主流を占めていたのは番傘という和傘でした。洋傘と言われるこうもり傘は
高くて買えなかったからです。市販品も少なかったのかも知れません。こうもり傘が一般家庭にまで普及するように
なったのは、ずっと後の事でした。
番傘は竹と木と和紙で出来ています。番傘の上の部分、つまり竹の骨を束ねている部分は木で出来ています。柄は
細い竹です。そして傘の部分の骨は竹を削ったもので出来ています。
子供の頃、幼友達のS君の家が傘屋さんでした。神辺という田舎町の表通りに面したところに作業場がありました。
作業場に入ると傘屋さん特有の匂いがしていました。傘の仕上げ工程で塗る柿渋と油の匂いです。時代劇には浪人
となった武士が傘張りの内職をしている場面が出てきます。おなじみのシーンです。あの場面を思い起こして見て下さい。
出来上がった骨組みに三角に切った和紙を一枚一枚丁寧に糊で貼っています。実に手間のいる仕事です。和紙を
貼った傘は天日干しにされます。高屋川の河川敷にたくさんの傘が干されていたのを思い出します。
それから先の詳しい工程は定かではありませんが、この上に柿渋を塗るのではないでしょうか。柿渋は一閑張りと
いわれるものにも使われているように和紙を丈夫にする働きがあるようです。そして、その上に油を塗ります。この
油は何というものかは分かりませんが、粘りのある油だったような記憶があります。新しい傘を開くとき油と油が
くっついてばりばりという音がしていました。しかし、時がたつに連れ油分が抜けていきます。そうなると簡単に
破れてしまいます。みんな少しは破れた傘をさしていました。すぐには買い換えが出来なかったからだと思います。
最近では番傘も高級品の和傘も日傘も工芸品のようになってしまいました。大量生産が出来ないからです。
こうもり傘が安くなり番傘が高くなると言う価格の逆転現象が起きてしまったのです。和傘も多くは中国からの
輸入品のようですが、観光地では地元の名産品として細々と作られているようです。
子供の頃、高屋川の河川敷に行きますと傘を干すための小さな穴がいくつも空いていました。その小さな穴の
中に、秋になるとコオロギが住み着きます。穴からあわてて飛び出してくるコオロギのことを、今でも懐かしく思い
出します。緑の草の上に列になって並んだ傘が懐かしい思い出の一場面として心の中に残っています。
2003年4月17日掲載
|
|
|
|