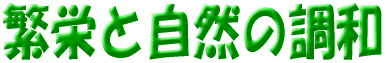
繁栄と自然の調和
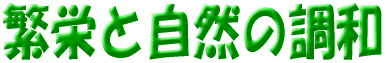
「文明の前に森林があり、文明の後に砂漠が残った」誠に言い得て妙な表現です。かなり以前の話ですが、中国で半ば
ホルマリン漬けのような遺体が発掘された事があります。保存状態が良くミイラ化せずに残ったのは地下の特殊な環境が
そうさせたのだといわれています。馬王堆という中国の前漢時代の王族の墓です。ここからは女性の遺体が発掘されました。
この墓には膨大な木材が使用されていました。何層にも仕切られた墓穴の中には、厚さがかなりあるような立派な板材が
惜しげもなくたくさん使われていたそうです。当時の交通手段ではとてもそう遠くからは運べないようなものです。しかし今、
墳墓の周辺には、そんな立派な木材を調達できるような木は一本も見当たらないそうです。考えられることとしては、当時
その地域が立派な木材を供給できるような森林があったと言うことです。今は黄土地帯の地味の薄い台地がどこまでも
続くような、緑の乏しい土地になっているそうです。
かつて、この地に文明があり、都市が栄え多くの人が住んでいた頃には立派な森があったのです。では森は何故なく
なってしまったのでしょうか。その原因はいくつかあると思いますが、一番大きな原因として考えられるのは、木材の消費
に対し木々の成長が追いつかなかったと言うことではないでしょうか。人口が増えるに従って様々な形で木材の消費は
増えていきます。それは家を建てるための材料であったり、かまどの燃料であったり、土器などの器を焼くための燃料で
あったのではないでしょうか。石炭や石油や天然ガスなど発見されていなかった時代ですから、燃料と言えば唯一木材で
あったはずです。 どれくらいの人口が存在したのか推し量る術はありませんが、これだけ立派な墓を築かせることが
出来る権力と財力を有する王族がいたのですから、この周辺には大きな街が存在したに違いありません。そうなると、
それに足るだけの消費があったと思われます。街が発展すればするほど、人口が増えれば増えるほど、ますます森林
は小さくなっていったに違いないのです。こうして森林がなくなると、都市としての機能を維持していくことも出来なくなり
次第に寂れていったのではないでしょうか。
それには天災も追い打ちをかけたかも知れません。森林がなくなれば土地の保水力もなくなり、保水力がなくなれば
田畑に引く水も枯れ農業も出来なくなってしまいます。保水力を失った土地に大雨が降ればたちまち大水となって人も
家も押し流してしまいます。こうして一夜にして都市がなくなったという例も少なくありません。森は全てを支える要だった
のです。それに気付かず植林もせずに切り出すだけ切り出して後には砂漠のような大地が残ったと言うわけです。
アマゾンの密林が失われつつあります。密林を支えている表土は非常に薄いものだそうです。その薄い表土にへばり
つくようにして木々が生い茂っているのです。薄い表土を一皮むけば下は地力のない赤土です。日本の山でも同じ事です。
自然は微妙なバランスの中で保たれています。一旦破壊が始まると容易に元に戻すことは出来ません。従って、人間が
常に環境を見守り、壊したところは修復を行うという努力を行わない限り、自然を維持することは困難なのです。ましてや
雨の乏しい地域に於いては、たゆまぬ根気強い努力が必要となります。一方自然が豊かになれば森や密林は雨を呼び
大地を潤し、保水力がありますから常に豊かな緑が保たれるのです。くれぐれも「文明の後に砂漠が残る」ような事だけは
避けたいものです。
2002年1月3日掲載
|
|
|
|