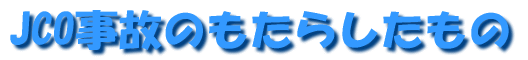
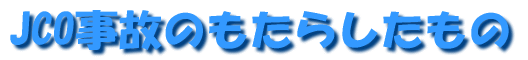
1999.12.13掲載
そもそも、先のJCOにおける臨界事故とはどのようなものであったのか、新聞にも取り上げられなかったような詳細な
資料が手に入ったので、要点をかいつまんで補足記事としたい。
JCOの事故は、高速増殖実験炉「常陽」に用いる為の極めて特殊な燃料の製造過程で発生した。「常陽」は小型の
実験炉で「もんじゅ」が立ち上がれば、その役目を終えるものだったが、「もんじゅ」の事故が再起不能なものであり、
常陽を改造して再立ち上げの必要が生じた。
(「もんじゅ」は冷却に用いていたナトリウムが洩れて、あわや大事故となるところであった。)
そのためには高濃縮のウランが必要となり、JCOに製造を依頼した。
極めて特殊なものであるだけに、本来なら高濃縮に適合した施設を作るべきところを、設備投資を惜しみ旧来の方法
で、手作業で作っていた。そのために、高濃度のウラン溶液を臨界設計の異なる沈殿槽に注入し、臨界量を超えてしまった。
このように、「もんじゅ」の事故が遠因となった連鎖反応的な事故といえる。
臨界を超えた沈殿槽では突発的核反応(バースト)によって、瞬間的に非常に強力な中性子線が発生した。
これが目撃証言による青い光(チェレンコフ光)の原因となったものだ。
これは中性子線が水の中を走るときに発せられる光で、隣室の人がこれを見たというのは、自分の眼球に中性子線が
飛び込み、水晶体の水を発光させたものと思われる。
直径45センチ、深さ60センチほどの小さな容器の中では、瞬間的に臨界に達した後も核反応は継続していた。
ステンレス容器が制御装置も遮蔽装置もないまま原子炉になってしまった。
深夜の決死隊が沈殿槽の冷却水を抜き取るまでの20時間、強い中性子線は四方に放出され続けた。
その間、周辺住民は長時間、中性子線の被爆が続いた。当初、関係者は中性子測定装置がなかったために、
臨界は最初の瞬間で終わったものと考えていたが、実はその後もずっと続いていたのである。
しかも中性子線の測定が行われ、臨界状態が続いていることが分かってからも、住民サイドには知らされず、
その間、住民は被爆し続けていたことになる。これは極めて重要な、意識的犯罪といわざるを得ない。
臨界状態は、我が身を犠牲にしたJCO職員を中心とする決死隊の働きによって終息を見た。
しかし、いったん強い中性子線の被爆を受けた建物や周辺の土壌は放射性物質に変わってしまった。
これを放射化という。とにかく土壌を中心とするこれらの物質が周辺に飛散しないように早急な対策が求められる。
チェルノブイリのように、これらの施設を覆い尽くすような施設が必要だ。
核廃棄物問題
今、国内には52基の原発が存在する。これらの内どれが事故を起こさないとも限らない。
原発に恩恵を受けているいないは別にして、もう一度真剣に核施設と同居している今日のあり方を考えてみたい。
原発は多くの廃棄物を発生している。この膨大な核のゴミを安全に処理したり、保管する方法は見つかっていない。
にもかかわらず、毎年どんどん蓄積されている。これらをどこかに埋めてしまおうという計画は随分以前からあった。
その候補地選びがこの岡山県でも行われている。一時は下火になったかに見えたその動きが、ここに来て再燃している。
候補地は哲西町の荒戸山である。岩盤が安定しており強固であると言うのが、その理由らしいが、ここは高梁川水系
の源流とも言うべきところです。もしこんなところにプルトニウムのような極めて毒性の強い高濃度の核廃棄物を
埋めて、それから洩れ出すような事があったら、下流域一帯は完全に放射能に汚染されてしまいます。
私達は足下に迫った問題として、一人一人が大変な問題を抱えているという自覚を持って貰いたいと思います。
|
|
|
|