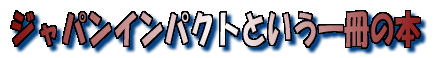
ジャパンインパクトという一冊の本
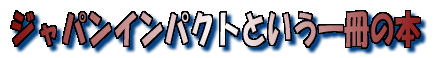
家内の父(私にとっては義理の父ですが)の趣味は彫刻でした。趣味とは言いながらも、作品が欲しいという人がいたら、
幾らかのお金で売りもしていたようですから趣味半分、仕事半分でもあったのです。大小の角盆や丸盆、取り込み盆
(お茶の道具をしまっておくもの)等に彫刻を施し、仕上げに漆を塗っていました。私は彫刻にも興味があったのですが、
何よりも仕上げに使う漆に大変興味を持ちました。漆については、それまで耳にすることはあっても、実物を見たことが
なかったからです。漆と言えば「かぶれの木」位の知識しか持ち合わせていませんでした。また、輪島塗り等のように
専業化された地域の事しか思い浮かびませんでした。こんな身近に漆が使われているとは思いもしませんでした。
彫刻されたお盆に塗られる漆には、色んな色の鉱物の粉が混ぜられ、美しい色に仕上げられて行きます。むろん、
彩色せずに生地漆のものもありました。漆は完成までに何層にも塗られていきます。また、仕上げには磨きという
工程もあります。そんな手間のかかる多くの工程を経ながら完成するのです。
漆塗りには人工の塗料には出せない美しさがあります。私もたった一度だけ彫刻から仕上げまでの工程を教わり
ました。しかし、残念ながら仕上げの工程で漆に負けてしまい、以来、漆に近づくことが出来なくなりました。もう一度
挑戦してみたいと思いつつ歳月は流れ、再び教えて貰う事なく義父が病に倒れてしまいました。今にして思えば、
義父が元気な内に、もっと本格的に教わっておけば良かったと後悔をしています。今も手元には義父が残していった
生漆や漆塗装に使う道具一式とお盆などの材料が残っています。
一般的に塗装はどんな塗料であっても乾燥が必要です。乾燥の条件としては風通しが良いこと、気温が高いことなど
です。しかし、漆塗りの乾燥条件は異なります。一般の塗料と大きく異なるのは湿気を必要とすることです。義父は
乾燥室を作っていました。大きな木の箱の内側には藁が張ってあり、漆塗りの作品を乾燥させる時は、霧を吹いて
藁を湿らせていました。私は乾燥に湿度が必要だという事を不思議に思っていました。義父もその必要性が何なのか
と言うことまでは知らなかったと思いますが、漆塗りを習った時から、漆の乾燥には湿気が必要だと教えられていた
のだと思います。室に入れるもう一つの理由に漆塗りは埃を極度に嫌うと言うこともあります。漆の乾燥には長時間
を要します。その間、綿埃などが付くと、その部分が傷になって仕上がりがきたなくなるからです。
今、手元に一冊の本があります。「ジャパンインパクト」という題名が付いた本です。中を開くと漆の事など、日本の
伝統技術と言われるものについて学術的見地から詳細に書かれています。この本のテーマは日本古来の伝統的な
技法を見直すことによって、もの沈滞した産業の活性化や環境問題を起こさない商品の開発が可能なのではないか
と言ったことのようです。
漆は乾燥に湿気が必要ですが、その理由は漆の皮膜を形成する段階で、酵素が働いていることと密接な関係が
あります。塗料の乾燥に酵素が重要な役目を果たしているのは自然に産する塗料だからこそです。この生漆にヒント
を得て新しい塗料も開発されようとしています。環境にやさしい塗料の開発はこれからの必須問題です。現在の塗料
の多くは多量の溶剤を必要とするからです。溶剤の大半は大気中に放棄され多くの環境問題を引き起こしています。
この本には日本刀の技術についても多岐にわたって色んな事が書かれています。岡山県はかつて名刀の産地で
した。備前刀と言われる青江や長船(地名)などは、全国的にも名の知られた名刀の産地でした。岡山県には各地
に砂鉄の産地があり、たたら跡が残っています。県北で作られた鉄は船で県南に運ばれ、そこで刀や生活用具に
加工されたのではないでしょうか。
刀の切れ味と独特の粘りは鉄を鍛えることで得られる特徴のようです。そんな素晴らしい技術も大量生産の波の
中でいつしか忘れられていました。しかし、忘れられ忘れ去られようとしている、これらの技術の中にこそ日本古来
の伝統的な素晴らしい技術が秘められている事を忘れてはならないと思います。是非、みなさんに一読をお勧め
したい一冊の本です。
2003年6月14日掲載
|
|
|
|