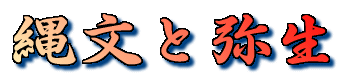
縄文と弥生
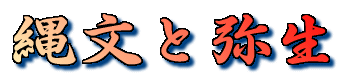
先日来、弥生時代は500年ほど遡るというニュースが報じられて来ました。そもそも弥生時代と縄文時代は
どのようにして区別するのでしょうか。今のところ有力な根拠とされているのは、発掘される土器や稲作をして
いたかどうかだそうです。
土器は縄文時代を通しての芸術性豊かなものから、弥生時代には実用本位のシンプルなものに大きく変化
します。また、時を同じくして稲作が盛んになっています。しかし、稲作が始まったという根拠は、土器と一緒に
発掘される炭化した籾殻や、盛んな稲作を裏付けるプラントオパールというものが、大量に検出された事などに
よるもののようです。
(プラントオパール=植物細胞の珪酸体 稲科の植物の葉にはガラス質の細胞が含まれており、葉が腐って
もそのまま残る)
この物質が縄文中期(約4500年前)とされる姫笹遺跡(岡山県)出土の土器から出てきた事が契機となり、
その後、朝寝鼻貝塚(岡山県)からは、ついに縄文前期後半(約6000年前)と推定されるプラントオパールが
発見されている。
ともあれ、全ては後の世の私達が定義づけた事であって、500年遡るとか、遡るのは間違いだとか、そんな
明確なラインがあるのでしょうか。現実には、緩やかに、ある時には激しくといった、潮の満ちてくる時のような
変化だったのではないかと私自身は想像しています。
縄文時代に稲作がなかったのかというと、これも疑問だと言われています。私達が学校で習った縄文時代は、
固定した住居を持たない放浪生活のような採取文化だったと教わって来ました。しかし、近年になっての相次ぐ
発掘から、定住し作物も栽培していたのではないだろうかということが、明らかになってきました。作物の中には
稗や粟といった穀物と一緒に、米も作っていたような痕跡が残っています。
確かに縄文時代は弥生時代に比べれば大量生産の時代ではなかったようです。必要なものを必要な量だけ
採取し、あるいは作って食べていたのではないかと思われます。従って、特定な人の元に富が集中するのではなく、
みんなで仲良く分け合って食べていたようです。
しかし、弥生時代になって生活は大きく変化したようです。それは大陸から渡ってきたという大勢の人が、この
列島に住み始めたからです。その社会は支配するものと支配されるものという、完全な階級社会だったようです。
富を得た者は権力をも手にし、稲作という大量生産型の作物を作ることによって、益々、富を蓄え権力を揺るぎ
ないものにしていったのではないかと思われます。
伝説の人物に日本武尊がいます。彼は武力を持って各地を転戦し、大和朝廷の基礎を固めていきました。
その過程で征伐されるのは、その地に昔から住んでいた人達です。恐らくは縄文人の末裔達だったのではない
でしょうか。争いを好まない、争いの手段を知らない人達を征服するのは、たやすいことだったに違いありません。
多少の抵抗はあったにせよ、大和朝廷軍は圧倒的な軍事力を有する組織的な集団です。
また、時には談合による平定もあったかも知れません。その証拠となる物が各地から出てくる刀や鏡ではない
でしょうか。刀には文字が刻まれ、金のメッキが施されています。当時にあっては、何ものにも勝るような宝物で
あったに違いありません。だからこそ、大切にされ今日まで残っていたのではないでしょうか。
このようにして時代は次第に縄文文化が弥生文化に置き換えられていったのではないかと思われます。振り
返ってみれば、わずかに二千年ほど前の話です。専門家にとっては500年という数字は大きな意味を持つもの
かも知れませんが、私達にとっては500年という数字より、時代の移り変わりという大きな変化そのものが、何に
よってもたらされたものなのか、また、その事によって人々の生活がどのように変化していったのかと言うことの
方がはるかに興味あるところです。
最近になってDNA鑑定による人間のルーツ探しが盛んに行われています。DNA鑑定で、どんな事が明らかに
なっていくのでしょうか。縄文人がどのように外来者と混血していくのでしょうか。長い対戦と融和との繰り返しの
中で、混血が進んでいったのではないかと思うのです。それは地球上の各地で繰り返された、征服するものと
征服されるものという葛藤の中で、民族の血と血が混ざり合うという歴史の繰り返しが行われたのではないかと
想像しています。こうして長い時間をかけて今日の日本人が形成されていったのではないでしょうか。いずれにせよ、
その背景には日本民族の壮大なドラマがあったに違いないのです。
2003年7月12日掲載
|
|
|
|