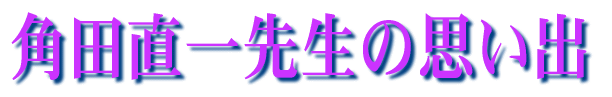
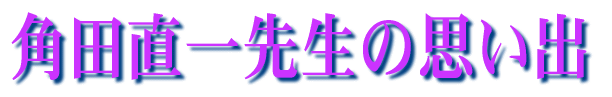
私と角田さんとの出会いは二度しかない。初めてお会いしたのは水島工場設立何周年記念かの行事の際であった。
記念行事の一貫として倉敷周辺の歴史について講演を聞いたような記憶がある。
そして二度目は児島の図書館で読書会があったときだった。このときは数人の人と一緒にお話をしたわけで、
角田先生は机を挟んで目前に座っておられた。
先生が書かれた本の内容に付いて感想を述べ、その後に呼松の歴史や鴨が辻(しかまがつじ)のいわれなどについて
質問をしたり、先生の説明を聞いたような記憶がある。温厚そうなそれでいてどことなく威厳のある先生だったような
気がする。先生はその時一度病気で倒れられた後でかなり弱っておられたようであった。
一度お宅にお伺いをして色々とお話をお聞きしたいと思っていた矢先、再度倒れられてあの世の人となってしまわれた。
今となってはどうしようもないことだが、本当に残念な事をしたと思っている。
縁というものはどこでどうつながっているか分からない。先年私の俳句の先生である冨士谷先生にお付き合いをして
児島周辺をまわったことがある。その際偶然に出た話の中に角田先生と冨士谷先生は仕事上の事で何度か児島で
あっておられることが分かった。どちらの先生もまだ現役で活躍されていた時期の事だった。
今ここに先生のサイン入りの一冊の本がある。「雁木のある風景」という随筆集だ。先生が地元の新聞「山陽新聞」に
寄稿されたものや、随筆として書き貯めて来られたものを随筆集として一冊の本にまとめたものだ。先生は下津井の魚問屋の
子供として生を受け、以来学生となってこの地を離れるまで長くこの地で幼年時代を過ごされた。
そして、一度は会社に就職されたが、故郷を思う気持ちは大変強く再び生まれ故郷に帰って来られ、
以来ずっと亡くなられるまで、生まれ育ったこの地に置いて活躍してこられた。
そして、幼年時代からの思い出をたどり、愛する郷土についてことあるごとに本にされ、数多くの本を残されている。
それらはすべて歴史の本であり、郷土史であり、民族学の本でもあると思っている。
すべての本を紹介できないのは大変残念であるが、文筆家としてもなかなかのもので、私のような浅学非才のものが
先生の書かれたものを論ずるのは大変おこがましいのだが、あえて言わせて貰うならば、文章全体が詩であり、
短歌であり、俳句であるような気がしてならない。
そして、単に郷土史を綴るだけではなく、そこには時代を見る鋭い目が光っていることも決して見逃すことは出来ない。
先生の残されたものは単に地元だけのものではなく、北前船の歴史などは遠く東北の酒田や大阪にまで足を運んで
聞き取り調査や文献を丹念に調べて歩かれている。これらは貴重な歴史資料だ。
最後に先生の書かれた文章の一端を紹介して、この項を閉じることとする。
この文章の一端は「教育の芳醇(ほうじゅん)」という随筆の中のものであるが、先生の心意気が充分に伝わってくる。
私はこれまで生きている瞬間を全的に生きてきたように思う。
人生に退屈したり、世をはかなんだりすることはなかった。たえず何かを考え、何かを書き、何かを準備するために勢力をすりへらし、いつも時間が足りないようであった。
長い時間をかけ、おびただしい精力を投入して、未知の分野の歴史知識を発掘して、一つの論文をつくり、一冊の
書籍に・・・・(中略)
人生とは準備することであるといった新渡部稲造先生のことばが、いつも私の傍らにあった。・・・・(中略)
そうして先生の文章は核心に触れる。
自分の語ろうとすることに、まず自分自身が感動をもつことが、講師たるものの第一の資格である。少し乱暴な言い
方かも知れないが、「講演とは、感動を彫刻する芸術である」と、私は常に自分自身に言い聞かせてきた。
と文章は続きます。なんでもないような文章でも先生の文章にはどこか人の心をとらえて離さないような魅力がある。
すべてを紹介できないのは大変残念です。文章全体が芸術であると言っても決して言い過ぎではないと思います。
角田直一随筆集「雁木のある風景」山陽新聞社刊
雁木とは言葉のみならず、そのものを見ることさえ少なくなりました。雁木は船の乗り降りのために作られたものです。
小さな港に行くと、石造りの石段のようなものが海縁にあると思いますが、これは潮の満ち干によって船の高さが
変わるので、乗り降りをしやすくするために設けられたもののようです。
先生の残された本の数々
・ しわく騒動記(塩飽の人名に敢然として挑んだ下津井漁師の壮絶な闘いの話)
・ 私の備讃瀬戸(先生の郷土愛を感じる一冊)
・ タコ壺あれこれ
・ 下津井風土記(随筆集)
・ 雁木のある風景(随筆集)
・ 路地と港町(随筆集)
私が持っている本はこれくらいですが、これ以外にも下記のようにたくさんあります。
・ 倉敷浅尾騒動記(幕末の倉敷、総社を舞台に長州第二奇兵隊の一軍がつむじ風のように暴れた)
・ 野崎武左衛門伝(児島の塩田王の事蹟と波乱に富んだ一生を克明に綴っている)
・ 十八人の墓「備讃瀬戸漁民史」(人名の島に起きた差別の歴史、人間性あふれる角田さんの大作)
・ 北前船と下津井港(北前船の航路をたどり下津井港との結びつきを明らかにした労作)
・ 備中兵乱「常山合戦」(宇喜多直家に図られ、小早川隆景に裏切られた三村氏一族の悲話)
|
|
|
|