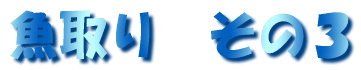
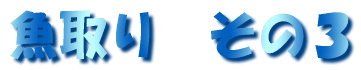
かに二題 (ずがに 、 つがに)
梅雨時期になると家の横を流れていた小さな川にも水があふれ、茶色く濁り始めます。隣のおじさんは魚が好きで、
梁(やな)を作り川に仕掛けます。青竹を割って、それを縄で編んで作ります。そうして川幅くらいのものが出来ると、
流れに沿って斜めに立てかけます。川は今日のように洗剤を流すわけでもなく、台所ものと言ってもわずかなものでしたから、
川も比較的きれいなものでした。梁を仕掛けてしばらくすると、蟹がやなを越えようと登り始めます。それを網ですくえば
良いのです。実に簡単な方法です。この季節になると、蟹は産卵のために川を下り始めるとも言います。あるいは、
上流から大水で流されて来ていたのかも知れません。とにかく、蟹の生態も良く分からないまま、この季節になると、
習慣のようにして、こんな仕掛けをしていたようです。
伊勢の川(鮎取り)
三重県の宮川の上流に、私の母の生まれ故郷があります。昔から林業の盛んなところで、町全体が杉や檜の深い山
に囲まれています。今は、宮川にもダムが建設され昔の面影は全くなくなってしまいました。
私達が母に連れられて母の実家に遊びに行っていた小学生の頃は、深く切れ込んだV字谷に、四万十川にも匹敵
するような清流が流れていました。今も滝見橋の上から見下ろすと、当時と同じような清流が見えます。ここはダム
よりは下手になるところです。僕らが子供の頃泳いでいたところは、今はダムの湖底になっています。V字谷の底を
流れる川は平地より低いところを流れていますので、川には共同墓地の横を通り、杉や檜の林の中を川に向かって
降りて行きます。河原には地元の人が屏風岩と言っていた、大きな岩が横たわっていました。
周辺には川の流れで角の取れた大きな石がごろごろ転がっていました。川の荒々しさを感じさせるような景色でした。
川の水は10分も浸かっておれないほどの冷たさでした。箱眼鏡で水の中をのぞくと、ずっと先まで見通せるような
清流でした。流れはきつく、激しい流れの中を鮎やハエといった魚がたくさん泳いでいました。
おじさんや一番年上のいとこは鮎取りの名人で、細い竿の先に針をつけただけの簡単な仕掛けで、大量の鮎を
ひっかけいました。引っかけという、この方法はこの地方独特の鮎取り法で、高度な技を要する方法だったようです。
おじさんも従兄弟も大変上手で、毎日たくさん捕まえてきては私達に食べさせてくれました。針も手作りなら、竿も仕掛
けも、みんな手作りでした。鮎は今とは比較にならないほどたくさんいたようで、形もサンマかと思うくらいの大きいの
がいました。大きなびくの中に入りきらず、折れ曲がって入っていたのが印象的でした。
取った鮎の大半は、その日の夕食のおかずですが、余ったものは焼いて串刺しにして藁づとにさしておきます。
こうして味噌汁のだしにしたり、煮物のだしにするのです。贅沢といえばこれほどの贅沢はありません。
川の中にはどんこといったり、ぎぎといったりする腹の底に吸盤を持った魚もいました。彼らは泳ぎが下手ですから、
流されないように川底の石に張り付いて生活をしています。僕らのように泳げない、鮎取りも出来ない子供達の格好
の遊び相手でした。しかし、泳ぎが下手そうに見えても手で捕まえようとすると、意外に俊敏でさっと逃げてしまいます。
こうして、川に入ったり寒くなると河原で暖まったり、屏風岩の側が僕らの遊び場所となっていました。
水泳の未熟なものはとても泳いでは行けないような急流ですが、地元の子供達の泳ぎの達者なものは川の流れを
うまく利用して向こう岸にまで泳ぎ着いていました。当時、少し山間部に入るとこんな清流がたくさんあったに違いあり
ません。しかし、今はもう、どんな川の上流に行っても滅多に目にすることの出来ない景色になってしまいました。
失われてしまった、もっとも美しい日本の原風景の一つだったと思います。
小川での遊び
夏休み伊勢の親戚の家に行くと、同級生のいとこが待っていたようにして、早速、近くの小川に水浴びに行きます。
小さな子供たちにとって、家の近くの小川は格好の水遊びの場所でした。山の方から流れてくる水は飲めるほどに
きれいで、そのかわり、びっくりするくらい冷えていました。石をめくると小さな沢蟹をたくさん見つけることが出来ました。
田圃の中を流れる川で、こんなにきれいな川があるだろうかと思うくらい、きれいな流れでした。たとえ田舎とはいえ、
当時の環境が本当に良かった証拠でしょう。
ちなみに今も変わらず、この清流はこの集落の田圃を潤しています。しかし、先年訪れた時には環境も変わり、沢蟹を
見つけることは出来ませんでした。
真夏とは言え、長くは入っていられません。少し入っては、そばの石の上に寝そべって体を温めていました。
元々平地より気温の低い山間部であり、1時間も水浴びをしているとすっかり体が冷えてしまいます。
裸で歩いてでも帰れるような距離であり、遊んで帰るとおばさんがトウモロコシをゆがいたり、スイカを切って待って
いてくれます。そんな事の繰り返しの楽しい毎日でした。
夕方近くになると、山からは降るようなヒグラシの鳴き声が聞こえてきます。いとこが裏の畑に行って大きなミミズを
掘って、蟹釣りの準備を始めます。掘った殿様ミミズを丸ごと細い針金にさして短い竿の先にくくりつけます。
そして蟹をすくい取るための網を準備します。この地方では蟹の爪に毛の生えているものを「ずがに」と呼んでいました。
地方によって呼び方は様々ですが、神辺周辺ではただの「かに」といっていました。僕らが泳いでいた小川の少し上流
に行くと水量が多くなり、川のコンクリート壁が壊れたところがあります。そこに殿様ミミズを差し込むと、やがて小さな
手応えがあって、そっと引き出すと毛の生えた爪が見えてきます。しかし、用心深く容易に姿を見せません。しばらく蟹
との駆け引きがあって、蟹の方がとうとう餌の誘惑には勝てず石垣の間から姿を見せます。その時をねらって網を
そっと蟹の下に差し込みすくい上げます。大きな見事な蟹です。身を切るような冷たい清流に、こんな蟹が住んでいる
とは実に驚きでした。神辺周辺では、この種の蟹はあまりきれいなところで目にすることはありませんでした。あるいは
そう言った環境がなかったからかも知れません。
こうして日暮れまでの1時間位の間に、3匹の蟹を捕って家に帰りました。それを早速、竃のところで残り火で焼いて貰います。
しばらくすると、蟹は真っ赤になってきます。焼きたての味は格別です。当時、私も弟も海の蟹も川の蟹も食べたことが
ありませんでしたから、蟹の味がとても新鮮でした。特に蟹みそは、今まで味わった事のない味でした。こうして夕飯前
のわずかな時間にすかせた腹を満たしていると、夕飯の支度が整います。夕飯にはおじさんといとこが捕ってきた鮎と
自家製の醤油や味噌で味付けした野菜が並んでいます。決して豪華ではありませんが、新鮮な川の幸と自家製の野菜
にぎやかな夕食が始まります。
食用蛙(牛蛙)
古くは食用にもしていたらしいですが、僕らはもっぱら遊びのために釣っていました。僕らが小学校の頃までは農薬と
いっても生き物を殺してしまうほどのものはなく、川にも野原にも、池にも田圃にも、いろんな生き物がたくさん住んで
いました。当然のことながら、蛙の種類も数も本当にたくさんいました。春先の水温む頃になると、田圃のほとりの水路
には、本当にお玉杓子がたくさんいました。これらは、梅雨の頃になると成長し、親蛙の仲間に加わってきますから、
田植えの後などは蛙の鳴き声で本当に賑やかでした。ほとんど一晩中鳴きあかしていました。子供の頃は、これら
蛙の鳴き声を聞きながら眠りについていました。
蛙の中でも一番大きいのが食用蛙で、別名牛蛙とも言われていましたいた。ぐーぐーと鳴く声は、牛というよりは何かの
うなり声にも似て、不気味な感じさえしたものでした。
この食用蛙を釣るのは実に簡単です。長い竿の先に「どんこばり」と呼んでいた太い針をつけ、針を覆い隠すように
赤い布をつけます。それを食用蛙がおりそうな池や堀の草むらで揺らします。すると食用蛙は餌と間違って飛びついて
来るのです。その時、布に隠れている針に引っかかるのです。小さな子供にでも釣れるというほどの簡単なものでした。
面白いほど次々に引っかかってきます。捕まえたからといって食べるでもなく、ただ面白いから釣って遊んでいました。
環境が変わり、池や堀も次第に埋め立てられ、食用蛙の住めるような環境も少なくなってしまいました。田舎の方を
旅行していて、ふと食用蛙の鳴き声を耳にすると、幼い日の頃が懐かしく思い出されます。ちなみに、僕らは食用蛙の
事を「しょっこん」と呼んでいました。
2000年9月24日掲載
|
|
|
|
|
|