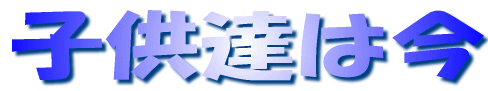
夏休みだというのに外で遊ぶ子供達の姿をほとんど目にすることはありません。子供達が汗を流しながら元気に走り
回る姿も声も聞こえなくなってしまいました。いつの頃からの事でしょうか。
先日もテレビで幼稚園や保育園に通う子供達に土踏まずがなく、姿勢が非常に不安定だという報道がなされていました。
又、別な放送では体温が異常に低い子供がたくさんいるとも言っていました。いずれもごく最近の話です。
歩くとか走るという人間にとって基本的な動きは、想像以上に身体のバランスを要することのようで、身体全体の筋肉
を使っており、それが刺激となって脳の発達を促しているのだとも言っていました。今の子供達がこのまま大人になる
と運動障害とまではいかないまでも、かなり機能的に欠陥を持った大人になってしまうとのことです。考えてみると
大変恐ろしいことです。
一方体温の低い子はどちらかと言えば夜型の子供に多いようで、昼間の運動量の不足と親達の生活と密接な関連
があるようです。こちらは運動量を増やしたり、家庭での生活習慣を変えてやることで急速に軌道修正は出来るようです。
いずれにせよ、かつて私達が子供であった頃には考えられなかった事で、今の子供達がいかに子供達らしからぬ
生活を余儀なくされているかという事が良くわかる事例です。
現代っ子達は有り余るほどのおもちゃを買って貰い家の中にとじこもったまま、大きくなってもテレビゲームに夢中に
なって、外で子供達同士がグループになって遊ぶという機会が非常に少なくなっています。
昔のように、学校から帰るやいなや家を飛び出し、友達を誘い合って狭い路地や近くの山や川を遊び場として飛び
回るような事はなくなってしまいました。
缶けりや石蹴りや鬼ごっこやかくれんぼと言っても、最早、現代っこには通じないのではないでしょうか。
おもちゃの質も変わってしまいました。私達が子供の頃の完成されたおもちゃと言えば、ブリキ製のゼンマイで動く
おもちゃでしたが、そんな高級な物は貧乏人の子供達には高嶺の花でした。私達のおもちゃと言えばコマやたこ、
紙メンコやマーブルと言ったものでした。路地裏をたまり場にして紙メンコに夢中になったり、マーブルで三角出しや
天登りと言った遊びに興じたものでした。
子供は子供達同士の集団の中で育っていきました。いじめたり、いじめられたりしながら大きくなってきたのです。
力の強いものや、体の大きいものや、年上のものが先頭に立って遊びを仕切っていまいた。弱いものは強いものに
どうやって好かれようかと腐心をしたものでした。そんな中から大人になっての世渡りのようなものを自然に身につ
けていったのではないかと思っています。力の強いものと言えども、頭のいいものや勉強の出来るものには一目置
いていました。力のないものは、あれこれと才覚を働かせて仲間の内での存在感を確実なものにしようとしていました。
一番どん尻のものだからと言って誰も無視はしませんでした。
仲間内にも不文律のようなものがあって、自分と同等位なもの同士の間では火花を散らしましたが、自分より弱い
ものや自己を主張しないようなものにまで、危害を加えたりいじめたりはしませんでした。弱いものをみんなでいた
わり引き立てひっぱていました。
従って、状況はどう変化しようとも常に仲間のバランスは奇妙に保たれていたような気がするのです。
仲間は常に気の合うもの同士、離合集散を繰り返しながら変化していました。
小学生も高学年になると行動半径も広がり友達の質も変わっていきました。遠いところの友達と往き来をしたり、
好き嫌いもはっきりしてきて、いつの間にか特定の友達とばかり遊ぶようになってきます。これが親友というものの
始まりではないでしょうか。猿の集団を見ていると、人間社会にも相通ずるような情景をしばしば目にします。
いかに人間という集団が野生から引き継いだものを色濃く残しているかと言うことが良くわかります。
そこに今日の子供世界の妙なゆがみを感じるのです。彼らには集団とは何なのか、仲間とはどういうものなのかと
言うことが良くわからないままに大きくなっているようなところがあるように思われます。
それは少子化だからと言うのではないと思います。集団で遊んだとか、徒党を組んで何かをやったとかという経験が
全くなく、常に個々が孤立しているからではないでしょうか。
もっと子供は小さい頃から集団の中で遊ばさなければならないと思うのです。年齢に幅のある、家庭環境の異なる
もの同士が集団で遊ぶ中から、自然に大人社会への準備がなされていくのではなかと思うのです。
何が正しくて何が間違いだと言うことを論ずるつもりはありませんが、少なくとも私達の子供の頃との違いを比較すると
集団と言う存在がなくなってしまい、妙に小さなこじんまりとした孤立化した人間が育っているように思えてなりません。
子供達はエネルギーの固まりです。有り余るエネルギーの発散場所がなく、常に母親の監視の中で、あれはだめ、
これもだめと言われ、外で遊ぶことも出来ず、家の中で鬱々として過ごしているような姿が目に浮かぶのです。
外で思いっきり成長のエネルギーを発散させてやりたいと思うのです。
そうすれば少年から青年になる精神的に不安定な時期も、もっと違う形で過ぎていくのではないでしょうか。
それは集団の中で学んできた自己という存在を、他との比較の中でより強く意識できるようになるからです。
比較する術も智慧もなく、自分自身を確かめる方法も分からず、ただうろうろとしている青少年達がもって行き場の
ない不平や不満を色んな形でぶちまけているように思うのです。
決してそれは教育基本法や青少年法などを変えて解決できるようなものではありません。そんな事をして子供達の
自由を奪ったり、将来の芽を摘んでしまうことは正に自殺的行為です。そんなことをすれば、ますます子供達の不満
は内向化して、とんでもない事件が、より一層増えてゆくことになるのではないかと懸念しています。
2000年9月16日掲載