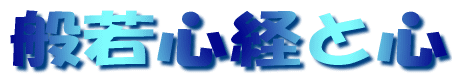
般若心経を勉強した際、心の存在というものについて改めて考えさせられました。
心とはいったいなんでしょうか。存在するようでいてなかなかとらえどころがなく、説明のつかないものです。
人はどんな時、心の存在を意識するのでしょうか。喜び、悲しみ、怒り、苦しみ、これら人生の中で起きる様々な
出来事を体験する度に、心の存在を意識せざるを得ません。
女(ひと)を愛すると言うことは、単なる肉体の結びつき以上に、心の存在なくしては考えられません。
人は決して一人では生きていけません。たとえ仙人のような生活をしていたとしても会いに行こうと思えばいつでも
会うことの出来る存在があるからこそ、一人で生きておられるのです。これが本当にたった一人であったとしたら
恐らくは孤独のあまり気が狂ってしまうことでしょう。
共に生きると言うことは、単なる人と人との有機的な結びつきではないはずです。その根底にもっとお互いに通じ合
うものの存在があるはずです。それが心というものではないでしょうか。
人間の体をどう切り刻んでみてもどこにも心の存在は見あたりません。しかし、私達は常にその存在を感じながら生きています。
それは肉体というものを超越した存在だからではないでしょうか。
ネアンデルタール人の墓地と思われるものを発見したとき、そこにはおびただしい花粉が確認されていたと言います。
すでに花の存在は消滅してしまっていたのですが、その花粉が残っていたのです。
彼らは愛すべきものがなくなったとき、その死を悲しみ、花で死体のまわりを飾ったのです。ここに他の動物を超えた
人間の姿を見ることが出来るのです。人間に心の存在なくしてこのような行動が出来るでしょうか。
確かに他の動物の中にも自分の子供を失ったとき、しばらくの間はその死体を引きずって歩いたり、悲しみの素振
りを見せるものもありますが、だからといって花で死体を飾ったり、埋葬したりはしません。
心ある動物だからこそ、とりうる行動だと思うのです。人間にも動物から抜け出し得ないような野蛮な行為や行動を
とることがあります。しかし、日常においては自己規制や物事の善し悪しを自分なりの基準の中で判断し、行動しています。
人を殺すことは良くないことであるし、人のものを盗むことも良くないことだと知っています。にもかかわらずそんな
行為を起こしてしまうのは、事の善悪が分かってやっている場合や精神的な歯止めが利かず、半ば無意識にやって
いるような事が多いのではないでしょうか。特に最近の事件は現実と想像の世界の区別がつかなくなっているような
ケースが少なくありません。心が壊れている状態だと言っても過言ではないでしょう。
釈迦はけっして人間の欲望を否定はしていません。むしろ生きる力として肯定しているようにも見えます。
しかし、一方では欲望に流れることを強く諫(いさ)めています。何故こんな相矛盾するような事を述べているのでしょうか。
そこには釈迦の深い洞察力があるような気がするのです。人間をがんじがらめに縛ってしまうことは人間自身を
殺してしまうことになる。さりとて規制のないままに放っておけば犯罪は増え、怠慢はますますはびこってしまう。
緩くたがをはめ自らが反省し、自己規制を行うことこそ肝要だと言っているように思えるのです。自己規制とは何でしょうか。
世の中を正しく見据える力を自らの修行の中で養いなさいと言っているように思えるのです。人間には教えられなくても
もって生まれた力がある。その力を自ら引き出しなさいと言っているようにも思えるのです。
その力を養うには「布施」を行いなさいと言っています。
もてるものはもてる財力を社会のために使いなさい。お金のないものは労力を提供して社会のために尽くしなさい。
財力も体力もないものは持てる心で悩んだり苦しんだりしている人に優しい言葉をかけて上げなさいと言っています。
そして何よりも大切なのは理論理屈ではなく、行動することによってのみ真理がつかめるのだと言っています。
百万弁のの理屈をとなえるよりも行動で示しなさいと言っています。その通りだと痛感しています。
現代人に何よりも欠けるのはこのことではないでしょうか。私自身も大いに反省させられる事です。
人を人が規制する。それは無理な話です。自分自身でさえも満足にコントロールできないものが、ましてや他人を
どうやってコントロールする事が出来るでしょうか。それは一人一人が異なる価値観や考え方を持っているからに
他なりません。それを心のフィルターと言っても良いのではないでしょうか。誰に教えられたものでもなく、人はそれ
ぞれ生まれながらにして異なった心を持っています。
その心という万華鏡のようなフィルターを通して世の中の出来事を見たり感じたりしています。
その見聞きした物は自前のフィルターを通して記憶の箱にしまい込まれます。やがて又、ある出来事が発生したとき
記憶の箱の中から再び過去の体験を自前のフィルターを通して取り出してきます。その取り出した記憶と目前に起
きている出来事を比較してみて、自分のとるべき行動や発すべき言葉を探しています。
我が子と言えども決して全てが自分と同じというわけではありません。自分とは生まれた時代も違えば環境も異なります。
赤ちゃんは母胎に宿った時から外界のことを敏感に感じていると言います。
と言うことは、この世に生まれてきたときには、すでに立派な人格を有しているという事になります。
子供は子供なりに一個の人格を持っているという事になります。決して親の私物ではないのです。ともすれば
親は我が子を見るときに自分の所有物のように見てしまいがちです。そこに今日的な悲劇も発生しているような
気がするのです。親も子も共にこの世に生を受けた人間同士として共に尊重しあって生きなければならないのでは
ないでしょうか。人の親になって見れば良く分かることですが、自分自身の意のままにならないことばかりです。
腹の立つこともいっぱいあります。それが子を持つ親というものです。自分自身も子によって育てられていると言って
も過言ではありません。意に添わぬ事、親なればこそ心配もし、悩みもして自分自身も成長させられているのだと思うのです。
大変複雑で難しい世の中になりました。しかし、考えて見ればいつの世でも悩みもあれば苦しみもあるのです。
飢えることなく食べていけると言うことだけでも幸せな事かも知れません。つい百数十年前までは、いや戦前の
一時期や戦中戦後においても飢えに苦しんだ時期はあったのです。
豊かなる時代に何故心だけが飢えたように心寂しくなっていくのでしょうか。不思議と言えば不思議です。
人がこの世に存在する限り、永遠のテーマかも知れません。遥か二千年以上も前のお釈迦様の時代にも
今の世と全く変わらない人間の悩める姿があったことを思うとき、人間の存在とはいったいなんだろう、人間の
心とは何だろうと妙に哲学めいた思いにとりつかれてしまうのです。
2000年9月16日掲載