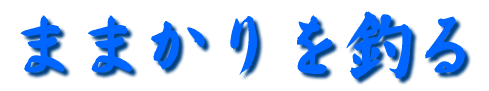
釣り紀行 その2
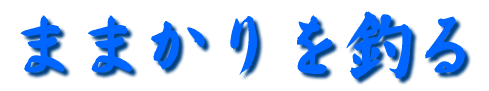
初めて船釣りを経験したのはもう30年以上前になる。
すでに亡くなった親友が誘ってくれたのがきっかけだった。
そのころの瀬戸内海は水島コンビナートが運転を開始していたとはいえ、まだまだきれいな海だった。
もちろん生活排水も少なく、海の水は透き通るように澄んでいた。
「ままかり」という魚は江戸前では「こはだ」という魚に相当するのだろうか。詳しくは分からない。
岡山県では昔から「ままかり」といっていたらしい。語源も定かではないが、一説によるとあまりにもうまい魚なので
ついつい食が進み隣の家のご飯(まま)を借りに走ったことから、そう言われるようになったという事だが、
おいしいおいしくないというのは多分に個人の味覚によるものなので何とも言えない。
ただ一つだけ言えるのは瀬戸内海、特に岡山県ではそれくらいポピュラーな魚だということになる。
|
|
この魚、潮の流れの早いところを集団で泳いでいる。
私が親友に連れられていった日も、ひとしきり赤メバル(正式にはかさご)を釣った後、引き上げるまでには
もう少し時間があるからと、水島沖の島近くに船を寄せた時だった。
澄み切った海の中を潮の流れに逆らうように、小さな魚の群が実に何万匹といっても良いくらい、とぎれることなく
泳いでいるではないか。それが「ままかり」を間近に見た最初の経験でした。
それは、あたかも海の中に川が流れているように見えていた。さよりなども時として集団で潮の流れに逆らって
泳いでいることはあるが、生まれて始めてみる海の中の出来事であったことと、あまりにも水が澄みきっていて
海底が間近に見えたことが印象を、ことさら強くしたのだろうと思われる。
今でも鮮やかに、その時の状況を思い出す。海の中に川が流れている。
|
|
それからずっと時代は下がり、近年の事になる。海の水は確実に汚染が進み、とても海底をのぞき見ることは
出来なくなってしまった。この日も赤メバルを目的に船をチャーターしたが、ほとんど釣果なく、仕方なくシーズンが
終わりかけているグチを釣った。(グチ釣りについては又別の機会に書こうと思っている。)
仲間のたっての希望で昼食後の帰り船で「ままかり」を釣ろうということになった。
初めての時もそうであったが、仕掛けは至って簡単、餌なしのさびき釣りである。
潮流の激しいところほどよく釣れるので、碇をおろし、船を固定して釣り糸をおろす。
船の周りは潮がどんどん流れている。釣り糸を下ろすか下ろさないかで、こつこつとした当たりがある。
そんな当たりの感触を楽しみながら糸をたぐり上げると、鈴なりのように「ままかり」が疑似針にかっている。
中には小さな鯖やアジ、イワシまでも混ざっている。海底を透かして見ることなど、とても出来ないくらい水は濁って
いるけれども、海の中の豊かさは今も昔も変わらないように見える。
釣りに夢中になっていると、突然、海面がさざ波立ち始めた。と見る間に小魚が船の舳先(へさき)と同じ方向に
海面を飛ぶように泳ぎ始めたのだ。イワシなどの小魚が大きい魚におわれて逃げまどう様は時々見かけることは
あるけれど、こんな光景を目にするのは初めてだった。水面だけでも数え切れないくらいの数だから、
ましてや海の中は想像にあまりある光景だろう。まるで手を差し出せば手に当たるくらいのおびただしい数なのだ。
船べりをたたくように泳いでいく。
海は豊かだという実感をこの時ほど感じたことはない。
|
|
どんな魚でも骨があるし、鱗がある。食べる前の処理を誤ると、どんなにうまい魚でも台無しになってしまう。
しかし、小魚ともなると、そう簡単にはいかない。勢い、横着できる方法はないかという事になる。
手っ取り早いのは、鱗を焼いてしまい、骨は三杯酢で柔らかくして、頭から食べてしまうのが一番簡単な方法。
少し丁寧にしようと思えば鱗をとり、頭を落とし、腹を出して酢に漬ける。食べるときは骨毎でもかまわないし、
早めに食べるときは骨だけをしごいて抜き取って食べる。
焼いて三杯酢に漬けても、生を酢に漬けても食べ頃は、少なくとも一昼夜おいてから位の方がおいしい。
一杯飲み屋などではカウンター前においた大きなどんぶりの中に,山盛りの「ままかり」を入れておいている。
焼くのがうまいのか漬けるのがうまいのか、程良く身が締まり、骨もほとんど口に当たらない。
それこそ「まま」ならぬ、酒がもう一杯余分に飲めるというもの。
演歌を聴きながら「ままかりの酢漬け」で一杯、考えただけでも楽しくなるではありませんか。
|
|
|
|
|
|