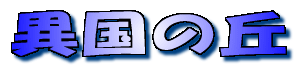
異国の丘
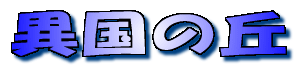
「今日も暮れゆく異国の丘に友よ辛かろ切なかろ・・・・♪」と続くこの歌は、私がものごころ付いて最初に覚えた
流行歌ではないかと思います。歌詞の意味や歌の背景など良く分からないまま歌っていました。それでも歌詞の
ところどころから、この歌は遠い国にいる兵隊さん達の歌だと言うことは分かっていました。
この歌の作曲は吉田正さんですが、歌詞は誰が作ったのかハッキリしないようです。恐らく、戦地にいた人達の
思いを、歌心のある人が代筆したのではないでしょうか。この歌の題名である「異国の丘」とは、満州かあるいは
ロシアの抑留先のものではないでしょうか。寒風吹きすさぶ北の大地での生活は、想像以上に厳しいものであった
に違いありません。凍える手と手をこすり合わせながら、背中を丸めて寒さに耐えている兵隊さん達の姿が目に
浮かぶようです。もの悲しくやるせないこの歌が、何故、幼い私の心に残ったのでしょうか。苦もなく覚えてしまった
歌のような気がします。
戦後は歌の移り変わりと共に変化をして来ました。明るい歌もありました。その代表は「赤いリンゴに唇寄せて
黙って見ている青い空・・・・♪」と並木路子が歌った「リンゴの唄」です。見たことのないリンゴのふる里、北の国の
美しい景色を想像しながら歌ったものです。その当時のリンゴと言えば、この歌詞にあるような真っ赤なリンゴでは
なかったように思います。文字通りリンゴ箱という木で作った深い大きな箱に入っていました。中にはスクモが一杯
詰められていました。近所の八百屋さんでは、その中のリンゴを取り出しては磨いて店頭に並べていました。
「緑の丘の赤い屋根、とんがり帽子の時計台・・・♪」赤い屋根もとんがり帽子の洒落た家も見かけなかった神辺
では、ただただ想像するしかありませんでした。頭の中には、見たこともない外国の家のようなイメージが広がって
いました。恐らく連続のラジオドラマの主題歌ではなかったろうかと思います。
しかし、何と言っても衝撃的だったのは、美空ひばりの登場でした。映画と歌の宣伝効果は素晴らしいものでした。
名だたる俳優と競演したその姿には、子供心にさえ嫉妬を覚えたものです。「山の牧場の夕暮れに、雁が飛んでる、
ただ一羽、私も一人、ただ一人、青の背中で目を覚ます・・・・♪」今はただ断片的なシーンしか思い出せませんが、
その歌声はいつまでも印象に残りました。
「私の隣のおじさんは神田の生まれで、チャキチャキ江戸っ子、お祭り騒ぎが大好きで・・・♪」おなじみの「お祭り
マンボ」です。最近、盛んにリバイバルで歌われています。子供の時、両親に連れられて福山の田尻にあった海水浴
に行った時の事を懐かしく思い出します。福山駅からマッチ箱とあだ名された小さな鉄道に乗って行きました。閑散と
した海水浴場でしたが、両親に連れて行って貰った楽しい海水浴でした。その海水浴場で繰り返し流れていたのが
「お祭りマンボ」でした。
「星の流れに身を占って・・・♪」という、戦後を生きるためには、我が身を売らなければならなかった女達の思いを
歌った歌もありました。如何に戦後は過去のものになったとは言え、その傷は至るところに残っていたのです。
「ばちでぶたれて逆立ちすれば、山が見えます、ふる里の。わたしゃ、みなし子街道くらし・・・♪」美空ひばりが歌う
「越後獅子の歌」には、やるせない寂しさがありました。
こうして戦後復旧が急速に進む中で、流行歌もどんどん増えていきました。戦前から歌っていた歌手とは別に、戦後
登場してきた新しい歌手も多くなりました。
「春には柿の花が咲き、秋には柿の実が熟れる、柿の木坂は駅まで三里・・・・」♪青木光一の「柿の木坂の家」と
いう歌です。「泣けた泣けた、こらえきれずに泣けたっけ、あの娘と別れた寂しさに、山のカケスも鳴いていた・・・♪」
戦後大ヒットとなった春日八郎の「別れの一本杉」です。
御三家と言われた三橋美智也、三波春夫、村田英雄、そして北島三郎等の男性演歌界を代表するような歌手が
続々と誕生しました。
私達が多感な高校生だった頃、新御三家と言われる橋幸夫、舟木一夫、三田明等も高校生ものや股旅ものを
歌って華々しいヒットを飛ばしました。この頃からやっと戦後は過去のものとなり、新しい躍進の時代が始まりました。
米軍のキャンプで歌っていたというフランク永井がソフトな低音で歌った「有楽町で会いましょう」は、まだ見たことの
ない東京の姿を彷彿とさせるものがありました。
松井和子や青江三奈など実力派のムード歌手が活躍したのも、この頃の事でした。世は上げて観光や歓楽にと
浮かれた時代でもありました。何でも作れば売れる時代でもありました。給料も上がり、新しい家がどんどん建ち、
自動車も一家に一台という時代になっていったのです。
歌は世に連れ世は歌に連れ、そんな言葉が思い出されるほど、私の心には、その時代その時代の思い出と共に
流行歌の数々が浮かんで来ます。
2003年7月12日掲載
|
|
|
|