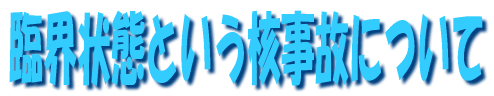
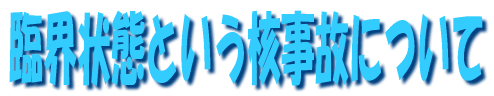
※ニガヨモギ(チェルノブイリのこと)はよもぎの変種で、茎が赤っぽいものやすみれ色のものがある。
MOX燃料について書こうと思っていた矢先に、とんでもない事故が起きてしまった。
使い古された核燃料を硝酸で溶かし、再処理する施設での事故だ。
臨界状態と言葉ではピンとこないが、これは明らかな核反応だ。事故の際、青い光が見えたと言っていたが
光を発すると言うことは、よほど大きな核反応と言わざるを得ない。
通常、原子炉では核分裂の元となる中性子をうまく制御しながら、ゆっくりとした核分裂を行っている。
中性子を制御しなかったら原子爆弾のようになる。そこまで反応が加速しないまでも、原子炉を溶かしかねない
ようなメルトダウンという現象を引き起こす。いったん、こうなってしまうと人間の手ではどうしようもなくなってしまう。
かってのチェルノブイリの事故がそうであったし、アメリカのスリーマイル島の事故もメルトダウン寸前までいった。
チェルノブイリの時は多くの被爆者が生じ、ヨーロッパ全土にまで被害は拡大した。被爆者の多くはいまだに
癌などの不治の病に苦しんでいる。
私は高校時代、原子力研究クラブに入っていた。当時はアメリカと旧ソ連が競って核競争をしていた時代だった。
アメリカが南太平洋で行った核実験により放射能がたくさん日本国内に降り注いでいた。
今日、各種の癌が増えているのは、あるいは、その頃の被爆のせいではないかと思っている。
それはそれとして、当時のクラブ活動での経験に少しだけふれておきたい。
私達クラブ員はワセリンを塗ったA4位の紙を近くの山の山頂に置いておき、1週間後に回収にいく。
回収した紙は焼いて灰にする。その灰をガイガーカウンターにかけて放射線量を測定していた。
校庭で採取した木の葉に乾板をのせた後、しばらくして現像するとフイルム上に放射能によって感光した部分が
わざと印を付けたように大小の白い点となって、点々とついていたことを驚きの目で観察したことを覚えている。
放射能はストロンチウム90とかセシウム137とか言った放射能だったように記憶している。
半減期の短いものもあり、気の遠くなるような長い半減期のものもあった。
放射能は目に見えない。もちろん色もなければ臭いもない。そしてどんなものでも簡単に透過してしまう。
それだけに恐ろしい。人間を含む生物に決定的な破壊力を持つ。
先の東海村の事故では戒厳令に近い警戒態勢がとられた。半径10kmの人は外出禁止という。そして一旦は
おさまったかに見えた臨界状態が再び再開したということだった。正に危機的な状況であったわけである。
追々事故の詳細は明らかにされるであろうが、事もあろうに事故処理の手順や緊急時の対応すら十分でなかった
という。消防署には被爆事故だと言わずに患者を運ばせ、消防士までもが被爆をしてしまった。被災者は40数名と
なったようだ。多くの被害者を出した背景には日頃の緊急時に対する取り組みがいかにずさんであったかが分かる。
東海村は日本における原子力研究の中心地として多くの原子力関連施設が集中している。
ところが半径350mの至近距離にも一般住民が住んでいる。超危険な施設のすぐ隣りに地域住民が住んでいる
ようなところで、こんな危険な作業が行われていたなどと、誰が考えた事があっただろうか。
ごく普通の町工場くらいに考えていたのではないだろうか。これがチェルノブイリの様な事故だったらと
考えただけでも、ぞっとするような出来事だ。
狭い日本、どこに住んでいても、のがれようはないのだが、せめて緊急避難訓練くらいは、日頃からしておく
べきではないだろうか。そして、地域住民に知らされたのは、事故が起きて相当時間経過してからであったと
言うことだ。これでは救われるべきものまでもが被災者になってしまう。
今回の事故は、国民や地域住民に核事故の恐ろしさや、私達がいかに核問題に無関心であったかを教えてくれた。
今後は各地で各施設に対する再点検が要求されるに違いない。その際、関連会社は隠し立てをせずに真摯な
気持ちで対応して貰いたい。
そして、MOX燃料については、この事故に覆い隠されてしまったが、本当に安全性に問題はないのか
確認をして貰いたい。聞くところによれば、日本の要求する基準値すら満たしていないような粗悪品もあるのだ
という。世界で、まだ一度も使用されていない新しい核燃料だ。本当に大丈夫なのだろうか。
今の原子炉も多くが老朽化している中で、先のような熱交換器の事故も発生している。
核分裂の放射能による炉の老朽化も進んでいるという。
そんな原子炉が新たなる核分裂の疲労に絶えることが出来るのだろうか。心配でならない。
今私達はダイオキシンと同じように人類が作り出した新たなる物質による新たなる危険性を抱えている。
原子力は使わないにこしたことはない。私達は今後、省エネにつとめ、新たなる危険因子を少しでも減らすような
努力をしないと、更に次なる東海村の事故を繰り返すことになるだろう。
1999.10.6 掲載
|
|
|
|
|
|