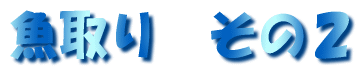
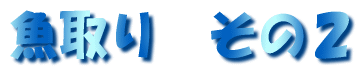
漬け瓶
私達が子供の頃にはハエ(魚のハエ)を捕る漬け瓶という仕掛けがありました。カボチャを引き延ばしたような形の瓶
の底に穴が空いており、中にハエの餌になるようなものを入れておきます。ハエは餌を求めて瓶の底の穴から中に
入ってきます。魚が瓶に入った頃を見計らって瓶を引き上げます。そして中の水と一緒に入れ物に移すのです。
余談になりますが、この瓶は蝿(あのいやな蝿です)を捕る蝿捕り器にも似ていました。蝿捕り器ををご存じでしょうか。
それこそカボチャに似た透明なガラス容器です。底には大きな穴があいており、周辺部は内側に向いて大きく折れ曲
がっており、その部分には水がたまるようにしてありました。瓶の上には水の入れ替えのための穴があいており、蝿を
捕る時には網か布で塞いでありました。瓶の底には足がついており、瓶の下に蝿の好きそうなものを置いておきます。
蝿は餌にたかり逃げようと飛び上がった瞬間に、瓶の中に入ってしまうと言う仕掛けです。瓶の底には水が溜まって
いますから、いつしかその中に落ち込んでしまうと言うものです。今日のように衛生状態の良くなかった私達の子供の
頃には、八百屋さんや魚屋さんのような店には必ず一個か二個置いてありました。蝿捕り紙と併用して使っていたようです。
話は横道にそれてしまいましたが、その蝿捕り器と構造がうり二つで魚のハエを捕る方は少し細長いのが特徴です。
細い長くしているのは瓶を横にして水の中に漬けて置くためです。この瓶を魚が入ってくる底の方を川下になるように
して川に漬けておきます。瓶の中には酒粕と米糠を混ぜ合わせて団子にしたようなものを入れておきます。魚たちは
餌の匂いに惹かれて瓶の中に入ってきます。面白いほどたくさん入って来ます。入った魚たちは瓶の底から逃げ出し
ても良さそうなものですが、人間が近づくとかえってあわててしまい逃げ出すことが出来ないようです。瓶の底が内側
に向いて折れ曲がっている構造のせいかも知れません。
誰が考えた方法なのか分かりませんが実にシンプルな方法です。当時、ガラス製品が結構高くて、その上ガラス製
ですから、ほんの少しでも石の角などに当てたりすると、すぐひびが入って使えなくなっていました。
子供の頃のほんのわずかな期間流行った魚捕りの方法です。今だったら瓶を作るにしても、もっと良い素材もあるだ
ろうと思いますが、もののない貧しい時代の思い出です。
ザリガニ釣り
ザリガニというエビは外観は伊勢エビに似て味も悪くはありません。かつては宮中の晩餐会などでの料理に用いられ
たと言いますから、由緒正しい食材でもあったのです。一方、食用蛙の餌として外国から持ち込まれたという説もあります。
いずれにせよ外国から持ち込まれ、日本全国に繁殖していったようです。僕らが子供の頃には、どこの川にもたくさんいました。
僕らが住んでいた家の近く、神辺高校の横を流れる溝川にも恐ろしくたくさんいました。決してきれいとは言えない川
でしたが、こんな川の方がこのエビ達にとっては住みやすい環境だったのだろうと思います。
もちろん溝川とは言ってもただ淀んでいるだけで、今日のように合成洗剤が流れ込むわけでもなく、水質そのものは
生き物達にとって全く問題のない環境でした。川の周辺は雑草が生い茂りカエルもたくさんいました。カエルの種類も
豊富で殿様ガエル、くそガエル、雨蛙、食用ガエル等々です。餌はこれらのカエルをつかまえて、殺してから皮をむい
たものを使っていました。残酷なようですが、一度に大量に殺すのではなく必要なだけ捕まえて使っていました。
現代と異なり、1匹や2匹殺しても自然は豊かで何ら変化はない時代だったのです。
釣りの仕掛けは実に簡単です。皮をむいたカエルにたこ紐を結わえます。そして手頃な長さの竹の先に縛って川の中
へ投げ込みます。こんな仕掛けを一人が3本くらい用意します。水につけて5分もすると、竿の先に結んだ糸がぴーん
と張ってきます。ザリガニが餌にさばり、持っていこうとしているのです。驚かせないようにそっとたぐり寄せるとザリガニが
餌にしたカエルにしっかりとしがみついています。その下にそっと網を入れてすくい上げるのです。
こんなことを飽きもせず、何度も何度も繰り返すのです。面白くて面白くて、それこそ家に帰るのも忘れて釣りに熱中
していました。親たちは子供達がいつまでたっても帰ってこないので、何かあったに違いないと、心配をして心当たりを
探し回っていたのです。親たちに不安がよぎります。もしかして池にでも落ちたのではないだろうか。ところが親たちの
心配をよそに、子供達はザリガニ釣りに夢中でした。幸いとでもいおうか、この場所は高校の裏手にありましたから、
夜間はほの暗いながらも照明があるのです。子供達にとってザリガニ釣りには事欠かない明るさだったのです。僕ら
が親たちの呼声を聞いて、これはまずいと思ったときは、時すでに遅しだったのです。親たちから大目玉を食いました。
それ以来、ザリガニ釣りに行くこともほとんどなくなりました。僕らも小学校を卒業し、そんな遊びもしなくなったのです。
そして公共事業が始まり、中小河川が整備され川はコンクリートで固められてしまいました。その上、農薬や合成洗剤
などが川を汚染し始めて、ザリガニもカエルも蛍も魚たちも急速に数が減っていきました。自然は私達の周辺から
遠い存在になっていったのです。今は昔のなつかしい思い出話になってしまいました。
へらブナをつかむ
いくら田舎だといっても大物の魚となるとそうたやすく取れるものではありません。今にして思えば、あの時捕まえた
魚は確かにへらブナだったように思います。
捕まえたのは田圃に水を入れる狭い水路でした。川の深さも子供が入れるくらいでしたから、さほどの深くはなかった
と思います。捕まえた場所は今でもはっきりと記憶に残っています。それほど興奮するような出来事だったのです。
季節だけがはっきりしません。夏の終わり頃だったのか、それとも秋だったのか、さして寒い季節ではなかったように
記憶しています。小学校の4年生頃の思い出です。友達3、4人で小川の側を歩いていたときでした。足下を驚いた
魚たちが驚いて泳ぎ去ったのです。何の魚か見分けはつきませんでした。鯉か鮒か。とにかく大きな魚でした。
しばらくは、どこまで逃げて行ったのか良くわかりませんでした。しばらく静かにしていると魚の背鰭が水面に出ています。
狭く浅い水路ですから、上手と下手から追い込んで捕まえようと言うことになりました。しかし、僕らは魚を捕まえられ
るようなものは何も持っていませんでした。家に取りに帰るにはあまりにも遠すぎました。仕方がないので、魚のいる
場所を中心に上手と下手に堰を作り、水を汲み出して捕まえようと言うことになりました。
いくら狭い水路だとはいえいざ汲み出すとなれば水は大量です。容易に汲み出せる量ではありません。みんなで
代わる代わる交代をして、1時間ばかりかけてやっと魚の姿が見える位まで汲み出しました。水が少なくなるにつれて
魚の姿が見え始めました。どうやら大きな鮒のようです。鮒は水が少なくなり、十分に泳げません。こうなると俄然
元気が出てくるものです。魚の隠れていそうな深みを目印にして更に堰を狭めます。そうしてまた水をかき出しますす。
こうして川底にほとんど水がなくなったころを見計らって、水路の上手と下手に分かれて魚を挟み撃ちにしたのです。
手や足の間をすり抜けようとする魚の感触が伝わってきて興奮が高まります。泥だらけになりながら、大声を張り上げ
て囲みを狭めていきます。そうして、とうとう一匹捕まえました。鯉かと思うような超大物でした。今まで大川で捕まえた
こともないような大きさの鮒です。結局魚は2匹いました。もっとたくさんいたのかもしれませんが、水路をせき止めた
時には他の鮒はすでに逃げていたのかもしれません。
大きな魚を捕まえたものの持っていた小さなバケツでは生かしておくわけにもいきません。魚が乾かないように草を
一杯かぶせて大急ぎで家に帰りました。家に帰って、たらいに入れてやると、さすがに大きな魚だけのことはあって
少しも弱ってはおらず大変元気でした。顔先が少しとんがった全体が鯛のように幅広い鮒でした。こんな大きな鮒が
あんな小さな水路にいたとは驚きでした。上流の池から流れ出てきたのかも知れません。その鮒をその後どうした
のか記憶にありません。家では淡水魚は食べませんでしたから隣のおじさんにあげたのかも知れません。
後にも先にもたった一度だけ、大きな魚を捕まえた経験談です。今はこの小川もなく、埋め立てられた田圃は団地に
なってしまいました。子供の頃の懐かしい思い出です。
2000年9月24日掲載
|
|
|
|
|
|